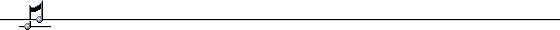Opinion : いまニックネームの心配をするフェーズ ? (2025/4/28)
GCAP (Global Combat Air Programme) の下で開発する次期戦闘機について、日本における名称として「烈風」が俎上にのぼっている、という話が出てきて、弊 TL がにぎやかなことといったらもう。
といっても公式に発表が出たわけではなくて、共同通信の「独自」と称する記事がネタ元。なにせソースがソースだから、「旧軍時代への回帰」みたいな文脈からぶっ叩いてやろう、という狙いがあるように見えなくもない。そして実際、そういう文脈で吹き上がる人が出てきている。
ともあれ、公式な発表が出ていない以上、あまり真に受けすぎてカッカしたり口角泡を飛ばしたりするのも考え物。まだ、大喜利のネタにして遊ぶぐらいがいいのではないかというのが正直なところ。
にしてもまあ、よりによってその名前が出てくるの ? という感想はある。せめて、実戦配備にこぎつけた機体の名前にする方がよくない ?
よく、過去の戦史について「敵軍の方が被害が多かったから、○○は日本軍の勝利だ」みたいな主張をする人がいる。でも、それは結論を誘導するために話の筋をひん曲げている。本当に重要なのは「その戦闘行動を通じて達成したかったことを達成できたかどうか」。という観点から見れば、たとえばノモンハン事件の場合、お望みの国境線を画定できたのは蒙・ソ側なのは明白。
といった調子で書き続けていると脱線してしまうので、元に戻すと。
何をいいたいのかといえば、「肝心なのは、最終的な目的を明確に持っていて、かつ、それを達成する見通し・手段を備えているか、または状況に応じてアップデートできているか」。新戦闘機のニックネームをどうするかなんて心配をするよりも先に、やらなきゃならないことはわんさとある。まず、過去に信奉してきた「勝利の公式」が、今、あるいは今後に通用するという保証はないのだから、その「勝利の公式」を追求するプロセスは、常に走らせないといけない。
戦闘機に限ったことではないけれども、単に「優れた性能・仕様を持つハードウェア」だけあれば戦に勝てるものではない。技術的優越はあるに越したことはないけれども、あくまで必要条件であって十分条件じゃない。個人個人の技量もそうだけれども。
実のところ、ハードウェアの能力、あるいはそれを扱う個人の能力を、「正しい」相手に対して「正しい」タイミングで「正しく」ぶつけて、それによって初めて任務の達成、ひいては国家としての目標の達成・国家の生存につながるはず。
さらに、(大事なことだから何度でもしつこく書くけれども) 任務の達成を通じて、どういう所望結果を生み出し、勝利条件につなげていくのか、という考えを確固たるものにしておかないと、「戦闘」には勝てても「戦争」に勝てるかどうかが怪しくなってしまう。「戦闘に勝ち続けていれば、結果として戦争に勝つ」わけじゃない。
だから、そういう話をトコトン考え抜いて、ガッチリ詰めて理念を確定させて。その上で、「それじゃあ、ニックネームをどうしようか」というなら、まだ分かる。でも、そこまで話が進んでいるものなんだろうか。
もちろん、ここまで書いてきたことは、共同通信の記事が事実通りという前提での話。だから、そもそも「GCAP の下で開発する機体のニックネームについて検討している」という話がガセだったら、ハシゴを外されてしまうのだけれど。
とはいえ。この件だけでなく、「我が国主導」という体面を保つための言葉遊び、ともとられかねない話が伝わって来る様子を見ると、重点を置くべき項目をちゃんと分かってるのかなあ、という心配を払拭できなくて。
逆に、他国の機体 (に限らず、艦艇でもなんでも同じ) についても同様のところがあって。もちろん、ハードウェアやテクノロジーの面が気になるのは分かる。でも、そういうところ「ばかり」気にしててええんかいなと。
むしろ、その背後にあるはずのドクトリンとか CONOPS とか。そういう話に目を向けてみても、バチは当たらないんじゃないの ? だって、ハードウェアやテクノロジーはあくまで道具。それを通じて何を実現したいのか、こそが問題なのだから。
という方向で物事を考えるようになったのは、「ゲームチェンジャーという語の大安売り」をしばしば見かけるようになったおかげかも知れない。
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |