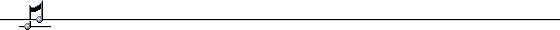Opinion : アジリティを発揮するということ (2025/5/5)
モータースポーツでもビジネスでも何でも、勢いに乗っている、常勝するチームや企業があると、「その勢いがずっと続くんじゃないか」と思ってしまう。逆に、なかなかうまくいかないチームや企業があると、これまた「ずっと駄目なんじゃないか」と思ってしまう。
ところが実際には、常勝チームが何かの拍子に没落したり、なかなか波に乗れなかったメーカーが何かの拍子に勢いに乗って大逆転 ! が起こったりする。
もっともモータースポーツの場合、いつも同じチーム、同じドライバーばかりが勝っていたら興行が成り立つかどうか怪しくなる。そのほか、安全面への配慮や経費抑制といった観点も無視できない。だから、意図的にレギュレーションをいじって状況を変えようとすることがままある。そういう人為的な要素が入ってくるところは、ちょっと特殊かも。
もっとも実業の世界とて、政治あるいは政府機関が介入してレギュレーション (っていうのか ?) を変えることはあるから、似たり寄ったりの一面はあるかも。ただしそれだけとは限らず、当事者の頑張りあるいは判断ミスによって、逆転劇が起きることも、もちろんある。
その「当事者の判断ミス」という話になると、よくあるのは、自著でも書いたことがある「成功の虜囚」。レーシングカーでも商品・サービスでも、何か大当たりしたときに、「これでいいじゃないか」といってその後の進化が止まってしまったり、状況の変化あるいはライバルの進化に適応できなくなったりする。
そうなると、ライバルに対して、付け入る隙を献上することになってしまう。もっともそれは、ライバルの側が「それならどうすればゲームのルールを変えてひっくり返せるか」を真剣に考えて、取り組んだ場合の話であるけれども。
妙なもので、一方がいろいろポカをやったり、過去の成功の虜囚になったりしているときに、それに付け入るべきライバルの側もまた、御丁寧にお付き合いして過去の成功の虜囚となることがある。
すると、過去にうまくいった手口を漫然と (?) 繰り返すだけになり、結果として逆転できずに終わる。ほんと、面白いというかなんというか。どこの業界の話とはいわないけれども。
怖いのは、そういう膠着状態のところに斜め上から違う種類の攻撃を仕掛ける輩が現れて、ごっそり持って行ってしまうことで。最近、あちこちの国の政界で、そんな種類の話を見かけるような気がする。 理想論を書くならば、「何かうまくいっても、次のラウンドでは前回の成功をリセットして、『今回はどうするのが最善か』をいちいち考えて、実行したいところ。もちろん、そうすることで必ず成功するという保証はないけれども、「成功の虜囚」になって動けなくなるよりはマシではないかと。
ただ、そこで「新たなアプローチ」を考え出したとしても、それが通用し続けるとは限らない。もちろん、最初からうまくいかないこともあり得る。たとえ、ある時点で有効性を発揮できる打ち手を思いついても、それを執行し始めた時点で、手の内はライバルにも知れてくる。そこで同じ打ち手を繰り返していれば、手の内を読まれる。
となると、常に状況を見ながら、有効性を見極めながら、細かく (または大きく) 軌道修正することを常に繰り返す。一種のアジリティ。
と、ここまでは自著でも書いた話と被る部分が多いけれど。
「『何でもできます』は『何もできません』と似たようなもの」という観点からすれば、ただ単に節操なく打ち手を変えるのは下策。あくまで、得意なこと・不得意なことを認識した上で、強みを発揮し続けるために打ち手を変えるのでないと。
ただし、その「強み」すら固定的なものではなくて、それすらも変化し続けるんじゃないかと思うようになった。そこで「うちの強みはこれだ」という不可侵の経典を掲げてしまうと、結局は硬直化してしまう。
「強みの認識」も、「それを発揮するための打ち手」も、常にうねうねと変化・進化させて、ライバルに先んじる・ライバルの裏をかき続けることが、「勝てる組織」に求められるんじゃないだろうかと。そんなことを考えていた。
なんとなくだけど、JADC2 (Joint All Domain Command and Control) の本質はその辺にあるような気もするよ ?
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |