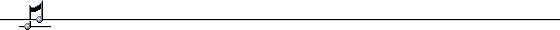Opinion : 名前の由来について知るのも楽しいよ (2025/7/14)
USS Michael Monsoor (DDG-1001) が横須賀にやって来てから一週間。自分は「ディテールを撮れるまたとないチャンス」とハッスルして、入港初日にスクランブル発進して撮りたいものを撮り集めてきたけれども、その後の動向を見ていると、とにかくもう見物に行く方が後を絶たない状況。
このまま、同艦がしばらく横須賀に滞在してたら、見物に来た人がついでに横須賀で緩行したり軍港めぐりのフネに乗ったり飲み食いしたりして、ちょっとした経済効果になるんじゃないか (米海軍は頭を抱えているかもしれんけど)。なんて話はともかく。
その USS Michael Monsoor に関連して面白い現象が起きていて。SNS 投稿を見ると、艦名の由来に言及している方が結構いらっしゃる。前にネームシップが横須賀に来たときには、そんな話は見かけなかったような気がするのだけれど。
その Michael Monsoor に限らず、米海軍の駆逐艦やフリゲートでは、戦功をたてた軍人、あるいは戦場で犠牲的精神を発揮した軍人を顕彰する命名が多い。将官クラスになれば、それなりに知名度があるケースが増えるけれども、下士官兵の命名だと「それは誰 ?」となる場面が多くて。
そんな中、今回みたいに「由来は何だ」と調べて、知る方が増えるのは、なかなか面白い現象。
そういえば、大物だと原子力空母の艦名になった Carl Vinson。よほど何か目立つことをしない限り、アメリカの議員の名前が日本で話題になることは滅多にないから、御存じない方が多くても無理はない。
でも、太平洋戦争が始まる前の海軍大拡張をプッシュしたのが Carl Vinson なわけで、海軍にとっては「重み」が違う。違う意味での「重み」があるのが、輸送艦の名前になってる Bob Hope。
ことにアメリカの場合、艦艇に限らず空軍基地でも AFV でも、果ては建物でも、個人名を冠する場面が多い。その名前の由来になった人物 (namesake) について知ることは、ちょっと誇張気味に書くならば、アメリカの、あるいはアメリカ軍の歴史をかじることにもつながる。
かつて米海軍の SSBN は、アイクか誰かが言い出したのを受けて「アメリカ史上の著名人」の名前をつけていたけれども、その 1 隻 1 隻の由来を調べることは、結果としてアメリカ史をかじることになっている。
それだけでなく、「どんな基準で名前をつけているのか」を知ることは、組織文化を垣間見ることにもつながる。「戦う組織」の観点からすれば、戦功をたてた軍人の名前をつける、歴史に残る戦闘があった場所の名前をつける。それはヘリテージを語り継いでいくということでもある。
と考えると、T-AO(X) で「人権活動家方面の名前をつける」としたのは、ポリコレ的には正しいかも知れないけれども、「戦う組織の命名ルール」としてはどうなのよ… と異論が出てきたのは、無理からぬ部分があるんじゃないのと思っている。
それと比べると、補給艦で「冒険家、あるいは何か冒険をした人の名前」を付けたのは、まぁいかにもアメリカ的というか。
たまたま「つかみの話題」の関係で米艦の話ばかりになってしまったけれども、他国でもそれぞれ、艦名あるいはその他の装備品の命名には、さまざまなルールあるいはこだわりといったものがあって。それは我が国でも同様… だけれども、陸自のアレは豪快に滑った感がある。おっと。
英海軍だと「伝統ある艦名」の再利用が多いという印象がある。それは裏を返せば、その名前の由来、あるいは同じ名を冠した艦の過去の活躍、といったものを大事にしているということ。31 型フリゲートの命名 (詳しくは世艦の拙稿を見てね) も、ヘリテージを大事にしようという姿勢が見える。
そんな、「ネーミングをとっかかりにして歴史や組織文化を知る」話って、肩肘張らずに相手の国や組織を知る、面白いきっかけになると思うので、ぜひ。
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |