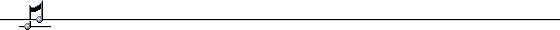Opinion : 抑止効果を発揮するには、と考えてみた (2025/8/11)
「核武装は安上がり」論というのが出ていて、当然ながら反論されている。
個人的には、「核武装は安上がり」論にはまったく不同意。それは、単にモノを作るためのコストだけの話ではなくて、それを何らかの運搬手段に載せて「武器体系」に仕上げる部分、それが実際に機能することを検証する部分、そして (仮にちゃんとできあがったとして) 配備した結果としての政治的コスト。そのいずれもべらぼうに高いと考えるから。
ただ、そういう数字の上での話だけではなくて、そもそもの核抑止という考え方に対して否定的な見方を示す意見もある。
「核兵器の存在そのものを否定するためには、核兵器が有用な存在であることを認めるのはよろしくない」という考え方をする人もいる。するともう、核兵器による相互確証破壊が有効であると認めること自体が、「悪」だから受け入れられないという話になってしまう。
もちろん、抑止とか相互確証破壊とかいう話が「相手がそれをどう受け止めるか」に依存する部分があるのは事実で、それ故に不確実な部分が残るだろうな、とは思う。思うけれども、その不確実な部分を減らす工夫はできるんじゃないかと。
「いちぜろ思考」で、抑止効果は 100% ではないのだから 0% だ、となってしまったのでは、極論に過ぎるでしょうと。
ただ、核戦力でも通常戦力でも、それが抑止効果を発揮するには、なにかしらの前提条件があるでしょ、というのが今回の本題。いいかえれば、「持っているというだけではダメよ」ということ。あっ、いきなり結論を書いてしまった。
「いちぜろ思考」が悪い方に出て、極端な話「我が国に侵攻してきたら核兵器で蒸発させるぞ」。これでは却って、相手が真剣に受け止めてくれないのでは ?
ブツがなんであれ、抑止というのは「本当にやるだろう」と思わせなければ抑止にならない。そこで実際にやった実績があればダメ押しの効果になるけれども、核兵器でそれをやるのは勘弁して。
核戦力を本番で使えば大変なことになるのは誰もが分かっているし、それだけに使用に際しては相応の「覚悟」が求められるというのが一般的なコンセンサス。すると、「簡単に使うもんじゃねぇ、使えるもんじゃねぇ」ということになる。デイル ブラウンの小説じゃないんだから、現実には、そう簡単にポンポンと核爆弾を爆発させられるもんじゃない。
そこで簡単に「使っちゃうぞ」と脅しをかけることが、果たして有効な脅しとして機能するかどうか。むしろ「口先だけで、実際にやれるはずがない」と受け止められそうではある。
だから、リアリティを持たせるためにも「段階」のようなものが必要になる。「ここまでは通常兵器で対処するが、このラインを超えたら核兵器を使うぞ」みたいなやつ。そこでは「国家として目指すエンド ステートと、それを実現するための道筋」という裏付けも必要になる。そこまでのピースが揃って、初めて抑止力として機能するんじゃないのかなあと。
ただし、「○○がレッド ラインだ」と宣言することは、そのラインを超えたら本当に「やる」だけの覚悟、相手にそう思わせるだけの気迫のようなものが付随していないと意味がない。それで、いざラインを超えたのに何もしなかったら、すべては台無しになる。誰のこととはいわないけれども。
何も核戦力に限った話ではなくて、通常戦力だって同じこと。人とハードウェアを持っているだけで「抑止」が成立するわけではなくて、それをいざというときにどう使うかという意図 & 意志の部分までがワンセット。
そこに、安全保障戦略とかドクトリンとか戦闘コンセプトとかいったものを公表する意味がある。そこで「手の内を明かしたくない」とかなんとか理屈をこねて、この手の話を表に出さないと、却って抑止力としての意味が削がれるんじゃないのかと。
すでに「やっちゃった実績」がある場合は別として、そうでなければ「本気でやるぞ、タダではおかないぞ、好き勝手にはさせないぞ」と相手に思わせるための仕掛けが要るわけですよ。裏を返せば、そういう条件設定の話抜きで「抑止効果の有無」を議論するのも違うんじゃないかと、
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |