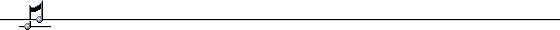Opinion : 抑止の掛け算 (2025/9/22)
なんか、潜水艦戦力の整備に関連して「次世代推進方式」を俎上に載せるとかいう話が出てきた様子。
といっても、実用できる可能性がある、まったく新手の機関が何か考案されたり開発されたりしているかといえば、そういうわけではない。となると、この「次世代推進方式」はまぁ、巷間いわれているように、原子力蒸気タービン主機を指すんだろうと考えるのが妥当ということになる。
でも、それに付随するコストであるとか、ノウハウの有無であるとか、実現して実戦配備・戦力化できるまでの時間軸であるとか。そういう諸々の話を考え合わせるに、「それ、いま持ち出す話ですか ?」という感はある。
前にも書いたか知れないけれども、「優れたハードウェア」と「優れた術力」だけで「抑止力」が成立するわけではない。この両者だけあっても、いざというときにそれを使うぞという断固たる意志を持ち、かつ、それを相手が理解していること。
それがないと、「あってもどうせ使えないだろ」ということになって、抑止は不成立になる。なにも国家間での武力紛争に限った話ではなくて、犯罪の抑止でも何でもそうじゃないのかと。「何かやったら警察が駆けつけてきて、とっ捕まる」と思うか、「何かやっても警察は来やしないよ or 捕まえられっこないよ」では、犯罪の抑止効果に大差がつく。
いざというときに、拳を振り上げてぶん殴れるのか。それはいま現在、東欧で実際に覚悟が試されている話。プー 1 号が、少しずつ賭け金を吊り上げにかかってきている中で、果たして NATO はどこまで「本気の覚悟」を見せられるのか。 「優れたハードウェア」と「優れた術力」があれば… という発想になってしまいがち (なように見える) のは、これはやはり「基盤的防衛力整備」という考え方の悪い置き土産なんだろうな、と思わざるを得ない。これが、政治的に無難な選択肢であったのは確かであるにしても。
もしかすると、「他所が持っているモノは、うちも持っていないと」「他所が持っている技術や能力は、うちも持っていないと」という考え方も、根っこは同じであるのかも知れない。「原潜待望論」は浮上したり沈んだりを繰り返しているけれど (なにせ潜水艦の話だけに)、そのひとつじゃないのかという疑いを払拭できない。
でも「力の空白を作らない」ということと「必要とあらば力を使うという覚悟と決意を示す」ことの間には、マリアナ海溝と同じぐらい深いギャップがあるのと違いますかと。大事なことだから何度でもしつこく繰り返すけれど、拳を持つだけでなく、拳をどう使って、何をどう殴るのかまで含めて考えないと。
抑止力というのは「物理的なハードウェア」「それを扱う術力」に加えて「その術力をどこにどう向けるのかという運用コンセプトや、その土台になる教義」「それらを支える兵站などの基盤」などの諸要素も含めた掛け算であるはずで。掛け算だから、どれかの要素がゼロになればアウトプットはゼロになる。
え、「そういう結論に誘導するために、わざと掛け算ということにしてるんじゃないか」って ? いやいや。どんな強力な装備と人員がいても、使う決意がない or 有効に使えないのでは「武力」にはならないのだから、掛け算で正しい。
これは「核武装論」についてもいえることで、持ってるだけで抑止力になるわけじゃないだろうと。その辺、北の刈り上げ君がどういうつもりでいるのか、ちょっと興味がある。
そういう話になると、武力行使の話に限らず、内輪もめや政局ばかりやっている国は、「足腰がしっかりしていないんじゃないか」といって甘く見られる可能性があるんじゃないか。そんな話も出てこよう。認知戦工作に対する脆弱性みたいな話も、同様に考慮に入れる必要がありそう。
そういう話になると、民主主義国家よりも、強権的な国の方がどうしても有利になりがち。じゃあ、そこのところのギャップをどうやって埋めればいいのか。そんなことだって考える必要があろう。
要は、「形のあるモノ」だけが抑止力じゃないよという話。
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |